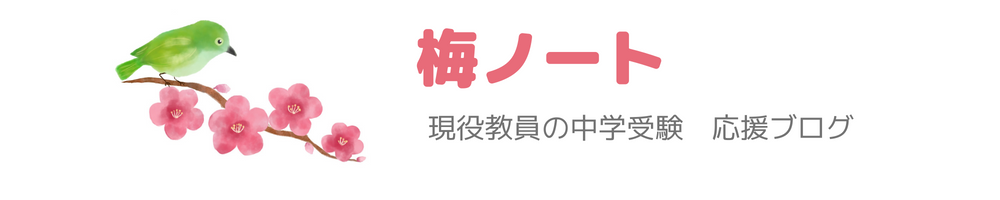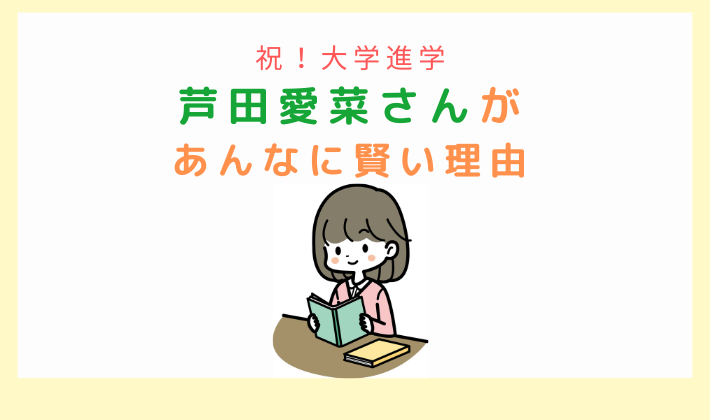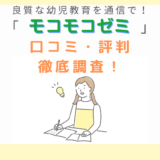天才子役として有名な芦田愛菜さん、中学受験を経て2017年に慶應義塾中等部に進学し、この春、慶應義塾大学法学部政治学科へ進むことが決まったそうです。
幼いころから大活躍。中学受験の勉強のために1度メディアに姿を現さなくなるものの、復活後かつての勢い以上に、番組やCMに引っ張りだこです。
彼女の発言はいつもとてもしっかりしていて、大人が聞いても感心してしまうことばかり。
そんな彼女がどんな幼少期を過ごしていたか、どんな学びを経ていたかを中高の現役教員が考察してみました。

芦田さんのような子どもに育ってほしいと思う保護者の方も多いはず(我が家も憧れ…)
芦田愛菜さんが短期間の受験勉強で難関中学校に合格した理由

芦田さんは「早稲田アカデミーEXIV校舎西日暮里校NN女子学院クラス」に通い、受験直前は10時間ほど毎日勉強していたようです。
中学受験の早期化が進むなかで、芦田さんが短期間の勉強で、偏差値70ほどの学校に合格できた理由は
「読書習慣」が大きかったとされています。
小さい頃からたくさんの読書を通して想像力を膨らませ、それが、中学受験に必須の「考える力」の土台になったようです。
今回は芦田さんの本「まなの本棚」やインタビューを参考に、彼女の勉強との向き合い方を考えてみようと思います。
この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
「考える力」をつける方法①:読書で「基礎学力」を固める
芦田さんが本を好きな理由は「頭の中で組み立てて世界を作っていく」ことができるからなんだそうです。
漫画やアニメ・映画と違って、読書は、物語の世界に形や色、登場人物の顔や声をすべて自分で考えて読んでいきます。
読書ってかなり頭を使う作業です。
伏線を回収する時には記憶をたどり、登場人物が多い時は、名前を覚えながらキャラクターの特徴を押さえて読み進めます。まだ知らない語句が出てきたら予想もします。
幼いころからの絵本の読み聞かせは子どもの脳にとても良いとされています。
受験勉強での暗記以前に必要な力は「基礎学力」です。基礎力を身に付けてさえいれば、短期間の勉強でも中学受験に合格することができます。
この「基礎学力」を身に付けるのにぴったりなのが、読書です。
基礎学力とは具体的に「日本語を正確に読み書きする力」です。どの科目でも教科書や問題文を正しく読めないと、学力向上につながりません。
入試問題が難しくなればなるほど、きちんと問題文を読めるかどうかが分かれ目になっていきます。
芦田さんが幼少期特にお気に入りだったというのがこちらの絵本
日本語の「オノマトペ」を繊細に表現した本で、我が家の1歳の娘も大好きです。
この絵本に出てくるような擬音語は、中学入試でそのまま問題になることがあります。
芦田さんが短期間で受験勉強を乗り切った理由のひとつは、読書量に比例した基礎学力の高さなのではないでしょうか。

彼女の女優としての表現力は、毎日の読書の積み重ねで磨かれているんですね
「考える力」をつける方法②:音読で語彙力やコミュニケーション能力を養う
読書好きの芦田さんは、何度か小説を書くことに挑戦したことがあるそうです。
本が自分の想像力を越えることに感動し、自分も想像力を豊かにしたい。と本で述べていました。
彼女は女優として、誰かの人生を演じることが必要なので、読書の経験が仕事そのものに役立っているんですね。
芦田さんの想像力の豊かさは、きっと並大抵のものではないんだと思います。素敵。
さて、誰かを「演じる」機会のない一般の人が、想像力を豊かにするためにはどうすればいいのでしょうか?
読書の中でもより効果的なのが「音読」です。
「音読」はどんなメリットがあるの?
- 語彙力・記憶力の向上
- コミュニケーション能力の向上
- 感情のコントロール・落ち着きが生まれる
- 集中力の向上
小学校の宿題で多いだけあって、良い効果がたくさん期待されています。でも私は苦手でした…音読。
目で見て、声に出し、耳で聞いて理解することで、語彙力が飛躍的にアップし、頭にも残りやすくなるそうです。
また、音読を行うと、脳の「前頭前野」に刺激を与えられることが研究で明らかになっています。
前頭前野が発達することで、自制心のコントロール・自主性の向上が期待できるとされています。
芦田さんは、多くの台本を読み、たくさん練習していたことで、この部分がかなり発達したのではないでしょうか。
音読は「考える力」をつけるためにも、おすすめの勉強法です。
「考える力」をつける方法③:読書を通して集中力を身に付ける
中学や高校で成績が良い子の特徴として、集中力と忍耐力があると感じています。
受験勉強って、もちろん楽しんでできることがベストですが、そんなに甘い世界じゃない。
どんなに賢い子でもきつい時間がたくさんあり、目先の楽しさよりも、未来の結果に対して、がんばらなくてはいけない。

どうしても精神年齢の高い子の方が、受験には有利だなと感じています。
芦田さんは小さい頃からずっと本を読むのが好きで、長い小説も少しずつ読めるようになり、自然と集中力が身についていったのだと思います。精神年齢も高そう。
やはり、読書は、学びの土台です。
では、長い時間本をじっと読めない子はどうすればいいのか?
まず、仕掛け絵本など、ビジュアル重視で、本を好きになることから始めましょう。
たとえばこのような仕掛け絵本は、小学生くらいになってもずっと楽しめます。無理せず、本自体をめくる回数を増やしていくと、自然と本棚に行くことが増えます。
中高生になって、読書から離れても問題ありません。幼少期の時に身についた本が好きという経験は、
大人になって、また、本を読むことに抵抗なく戻ってくることにつながります。
まとめ
芦田愛菜さんが難関中学に合格した理由は、幼少期からの読書経験が関係していました。
中学受験に合格するために必要な「考える力」を養う方法も、読書がキーポイントとなります
- 読書で「基礎学力」を固める
- 音読で語彙力やコミュニケーション能力を養う
- 読書を通して集中力を身に付ける
芦田さんの本は、子どもだけでなく、考える力を身につけさせたい保護者の方にも、おすすめの1冊です。
彼女の今後の活躍をずっと見守りたいと思うアラサーなのでした!